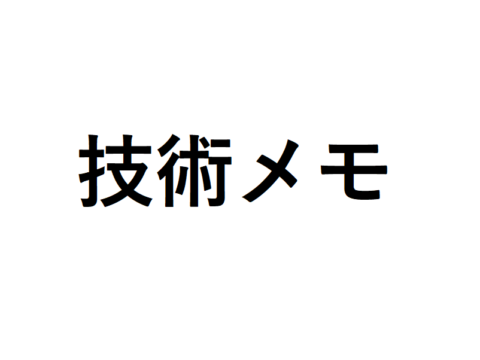
【技術メモ】fvOptionsで指定したポイントに一定の速度を与える方法のメモ
interFormを改造しfvOptionsを読み込めるようにした。今回はその続き。fvOptionsで任意の点に一定の速度を定義する方法のメモ。
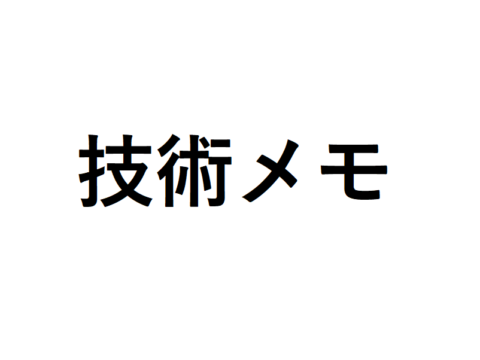
interFormを改造しfvOptionsを読み込めるようにした。今回はその続き。fvOptionsで任意の点に一定の速度を定義する方法のメモ。
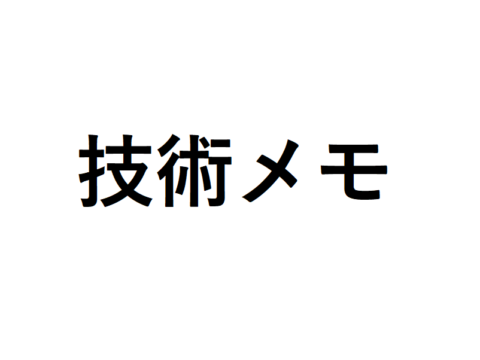
interFoam.CをいじってfvOptionsを読み込まそうとした時のメモ。作業の流れを簡単にまとめています。

QRコードスタンプを3Dプリンタ-でつくってみました。Tipsも簡単にまとめています。